福島区の花 のだふじの歴史
往古の昔、古大和川と淀川から多量の土砂が堆積し「難波の八十島」が生まれました。
上流から流れ着いた「フジ」が後に「野田州」と呼ばれる砂州に根付き、平安時代に末期には現在の野田・玉川付近にあった入り江一帯に繁茂していました。
鎌倉時代初期には太政大臣西園寺公経(さいおんじ・きんつね)が和歌を詠み、室町時代の貞治3年(1364年)には室町幕府二代将軍足利義詮(あしかが・よしあきら)が住吉詣での途中に「野田の藤」を見物したことが「義詮住吉詣」に記録されています。安土桃山時代の文禄3年(1594年)には豊臣秀吉も藤見に訪れたと伝わり、その後、「吉野の桜・野田の藤・高雄の紅葉」と童歌にも歌われ最盛期を迎えました。
戦前までは春日神社の境内に残っていた古木のフジは空襲で焼失、接ぎ木により子孫のフジは、区民の力により区内各所で開花するようになりました。(「のだふじ会」より)








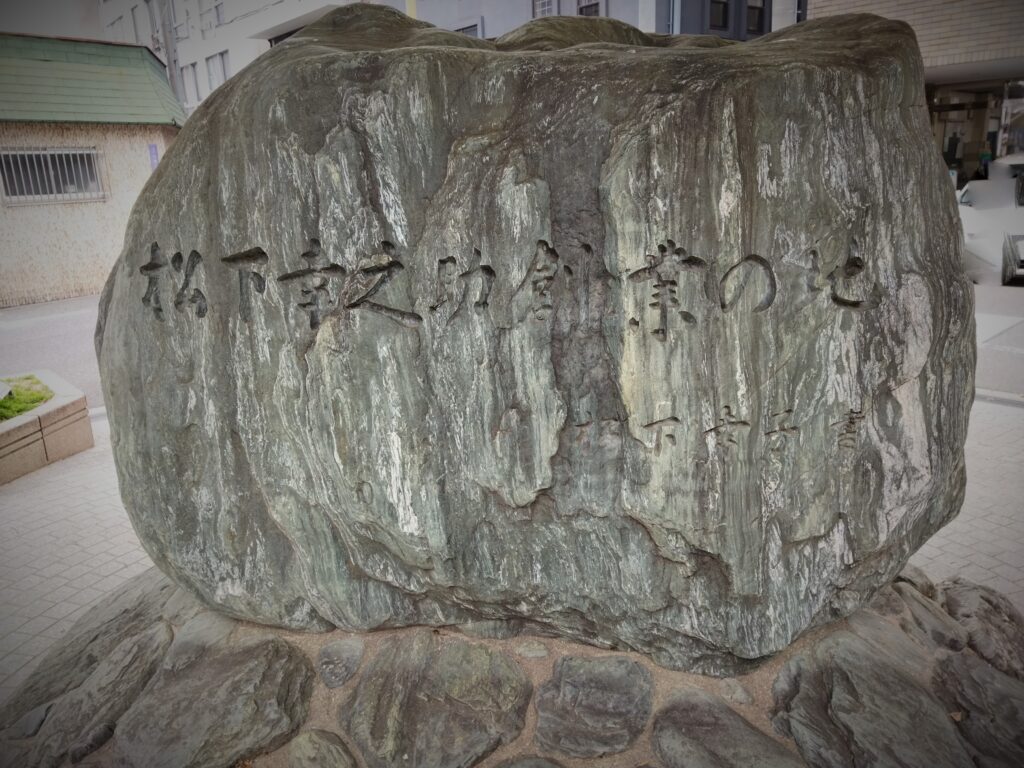
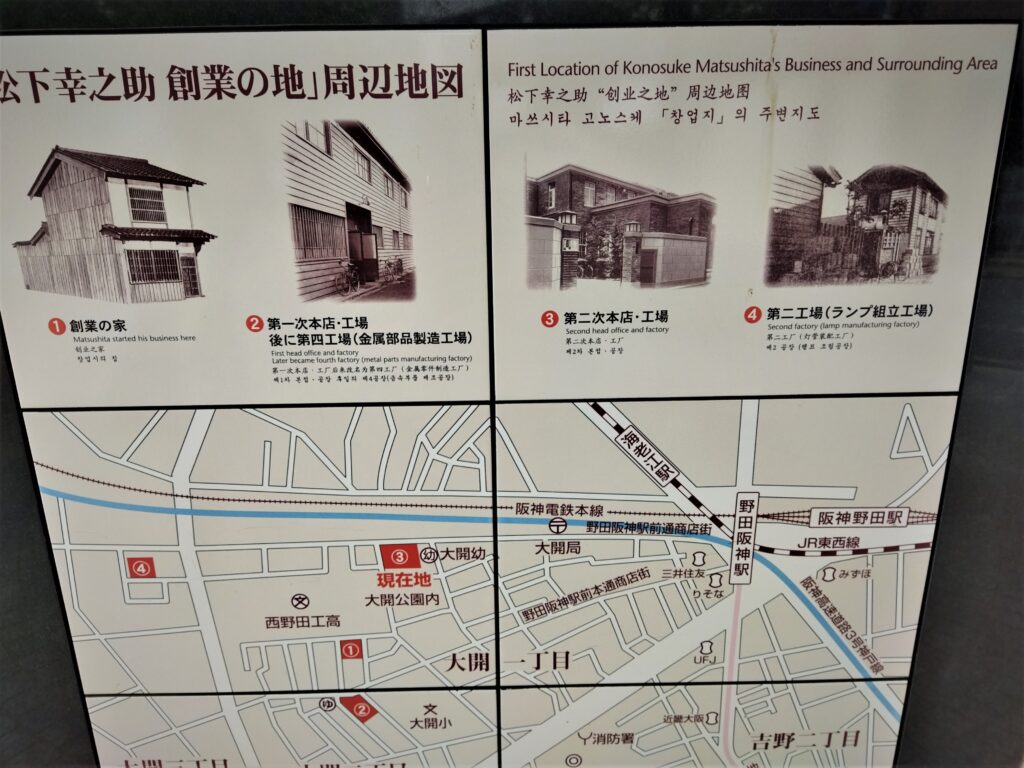


野田の藤棚は20数ヶ所に点在しています。平日だったのでリュックを背負ったご夫婦やお友達の方々などがカメラをもって散策されていました。
春日神社は住宅街にたたずむ小さな神社でした。これからも福島区の「野田の藤」としてもっともつときれいに花を咲かしつづけますように。
記:桃太郎




コメント